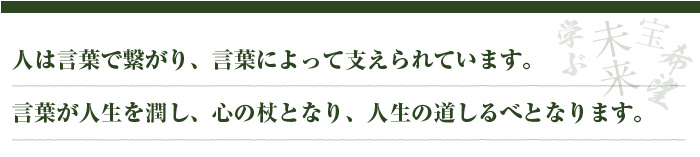「日本講演新聞」水谷もりひと編集長の社説から
考えさせられる話を一つ紹介します。
————————————-
小学生にはお駄賃も悪くないだろう
森浩美さんの小説『家族連写』は家族をテーマにした八つの短編集である。
その一つ『お駄賃の味』が昨年、筑波大学の国語の入試問題で出題されていた。
遊園地の専務をしている50代の裕之は、ある日、入場ゲートで
スタッフに呼び止められて困った様子の母子を偶然目にする。
化粧っ気のない母親と色あせたトレーナーの少年だった。
事情を聴くと、母親が持ってきた招待券の有効期間が過ぎているというのである。
母親は「うっかりしていました」と頭を下げ、小学2,3年生と思しき息子に
「これじゃ入れないんだって。今日は帰ろう」と言い、
踵(きびす)を返して駅に向かって歩き出した。
少年は母親に文句や不平を言うわけでもなく、ただうなだれて一緒に歩きだした。
裕之の心がざわめいた。その後ろ姿に少年時代の自分が重なった。
※ ※ ※ ※ ※
入試問題では、小説のこの冒頭のシーンが切り取られ、
いきなり小学5年生の裕之が登場していた。
時代は昭和40年代、工場で働く裕之の父親が病気で入院したこと。
母親はパートで働いていたが、家計は日に日に苦しくなり、
給食費を集金日に持っていけなくなったことなどが綴られていた。
ある日、クラスの女子児童の家が火災に見舞われた。
学校は全校児童からお見舞金を集めた。
数日後、担任の先生は裕之に、「これからお見舞金を持っていく。
おまえも一緒に来い」と言った。
児童会役員でも学級委員長でもない自分が何で?
とあまり気が進まなかったが、裕之は先生の車に乗った。
※ ※ ※ ※ ※
ここで入試問題は問う。
なぜこの時、裕之はあまり気が進まなかったのか述べよ。
※ ※ ※ ※ ※
さて、お見舞金を手渡した帰り道、裕之は先生から
「しっかりお役目を果たしたな。駄賃代わりに何か食べよう。何がいい?」
と聞かれ、「肉まんがいい」と小さな声で答えた(A)。
二人は車の中でホカホカの肉まんを食べた。
数日後、今度は放課後に呼び出され、「花壇の手入れを手伝ってくれ」と頼まれた。
作業は日没までかかった。そして先生はこう言った。
「手伝ってくれた駄賃代わりに、また肉まんでも食べようか」
裕之は躊躇なく「うん」と返事をした。
※ ※ ※ ※ ※
ここで入試問題は問う。
Aの「小さな声で答えた」から、「躊躇(ちゅうちょ)なく
”うん”と返事をした」裕之の心情の変化を説明せよ。
ここまでで入試の問題は終わっているが、物語はここから佳境に入る。
次の土曜日、先生は自宅の庭掃除に裕之を誘ったのだ。
掃除のあとは、奥さんの手作りの親子丼が待っていた。
久々の温かいご飯を裕之はむさぼった。
しかし、肉まんのことも、親子丼のことも母親には言えなかった。
その夜、ちょっとした親子げんかになった。
その際、裕之はつい口を滑らせた。
「母ちゃんのご飯より先生んちの親子丼は数百倍もうまいんだ。
うちが貧乏だから肉まんだって買ってくれるんだ」と。
母親は傷ついた。
翌日、裕之を連れて先生の家へ行った。
「うちは貧乏でも物乞いではありません」という声は震えていた。
「そんなつもりは・・・」と頭を下げる先生の言葉をしり目に、
奥さんが「夫は私のために裕之君を連れてきたのです」と割って入った。
この夫婦は5年前、水の事故で小学5年生の息子を亡くしていた。
その息子によく似ている生徒がいるという話を夫から聞いて、
奥さんが「一度会ってみたい」と言ったのだった。
そんな古い記憶がよみがえった。
裕之は帰りかけた母子に入場券を手渡し、少年に言った。
「君はうちのジャンパーを着て、ゲートで半権をお客さんに渡す。できるか?」
少年は1時間ほど仕事をした。そしてお駄賃として入場券をもらい、ゲートをくぐった。
※ ※ ※ ※ ※ ※
時代とともに、親の小遣いに対する考え方も、子どもの金銭感覚も、多様化している。
今、「お駄賃」は死語になってしまったのだろうか。
決して「お駄賃のすすめ」とか「お駄賃の必要性」を訴えているわけではない。
頑張った報酬として感謝の気持ちがこもったお駄賃がもらえる。
それはいつか忘れられない思い出になるということである。
—————————————
いろんなことを考えさせられる本ですね。
入試問題の中にも気になるものがありました。