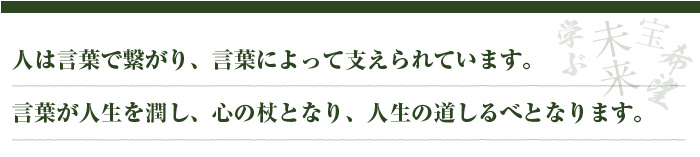志賀内泰弘さんのメルマガ『ギブ&ギブメルマガ 』から紹介します。
———————————
大好きな作家がいます。コラム・ノンフィクションの名手と呼ばれる上原隆さんです。
一番の代表作は、「友がみな我よりえらく見える日は」(幻冬舎アウトロー文庫)。
さまざまな悩みを抱える、どこにでもいる人たちにインタビューを試み、
時にほのぼの、ときにジンワリと心を震わせる文章を書かれます。
その上原さんの「喜びは悲しみのあとに」(幻冬舎アウトロー文庫)の中に、こんなお話が綴られています。
上原さんが、東京駅八重洲口のセルフサービスのカフェレストランに入ったときのことでした。
コーヒーを飲みながら本を読んでいると、72、73歳くらいの男性客が入ってきました。
彼がカウンターに近づくと、店員が、「ご注文ですか?」と尋ねました。
男性客は、なぜかボーとして立っています。
男性店員は、お客が答えないので、隣りの女性店員とおしゃべりを始めました。
男性客が、「私は目が悪いので・・・」と言うのが聞こえましたが、それでも店員はおしゃべりを続けていました。
再び、男性客が、「私は目が悪いので・・・」と言いました。
誰に言っているのかわからないよう口調なので、気が付かないようです。
上原さんが、店員に教えてあげようと思って立ち上がった時のことでした。
突然、身長190センチの黒人ウェイターが男性客の前に現れました。
ワイシャツに黒のボウタイ、タキシードに黒い前掛けを付けています。
そのとたん、男性客の顔がパッと明るくなりました。
両手で黒人ウェイターの手を握ると、言いました。
「あんたがいてよかった。」
ウェイターは、ニッコリ笑うと、トレーを持って来てカウンターの中の店員に指示。
そして、席に座った男性客のところに、生ビールとフライドポテトの乗ったトレーを運んできたのでした。
「ありがと。ありがと。あんたがいて助かるわ。」
「こちらこそ、ありがと、ございます。」とたどたどしい日本語で答えました。
上原さんは、この黒人ウェイターに興味を持ち、取材を申し出ました。
聞けば、ニューヨークのプロンクス生まれの30歳。貧しい家庭で育ちました。
25歳の時、日本に旅行に来て、日本人が人にやさしいことに惹かれて住むようになったそうです。
上原さんが、「お客さんに親切なのは、誰かに教えもらったからですか?」と尋ねると、こう答えました。
「家族の中、お父さんが毎日毎日いったの。
人はね、いつ死ぬかわかんないでしょう。
だから、あまりいいことしないで死んじゃったら、あなたの名前すぐ忘れちゃうでしょう。
だから、いいことして、死んでも名前、まだあるようにしなさいって。」
実にいい言葉です。
ここで、パッと、あることが頭に浮かびました。
私の母親が亡くなった時、友人S君から届いた一通のメールです。
「出張で告別式に参列することができない。
お母さんのこと、心よりお悔み申し上げます。
でも、最近思うことがあります。
人は死んでも、いなくならないのではないか。
例えば、作家や俳優が死んだという知らせを耳にしても、みんなの心の中に生き続けている。
だから、キミのお母さんは、ずっとキミの心の中に生き続けているよ。」
人はいつ死ぬかわかりません。
平均寿命が延びたとしても、それは統計上のことです。
病気や事故で、歳とは関係なく親よりも早く亡くなってしまう人もいます。
地震や豪雨の被害に遭う人もいるでしょう。
黒人ウェイターのお父さんのスゴイところは、死んでしまう前に、
好きなこと、やりたいこと、楽しいことをしなさいと言うのではなく、
「いいことして、死んでも名前、まだあるようにしなさい」と教えたことです。
きっと、彼は、目の不自由な男性客だけでなく、多くの人たちから慕われているに違いありません。
縁起でもないことですが、もし、今、死んでしまったとしても、大勢の人たちの心の中に生き続けることでしょう。
有名な大リーガー、総理大臣、アイドルグループのセンター、芥川賞作家、宇宙飛行士・・・にならなくても人の心には残りうる。
ここに、一つの誇るべき生き方があります。
————————
自分のことが、みんなの心の中に残るように行動したいですね。
できる事から一つずつやってみます。